私は少し前にとある病気で入院しまして、誰かがお見舞いに来るとしたら、おそらく持ってくるであろう、お見舞い封筒の存在が気になった、ひでぽんです。
今までの自分を振り返ってみると、実はお見舞いの際、お金を包んだ封筒を持って行ったことがありませんでした。
気づけば自分も今30代。さすがに一般的なマナーを知っておくべき。
私は「お見舞いのお返しなんていらない」というタイプなので、お見舞い封筒に自分の名前を書くのに躊躇しそうです。
しかし、調べてみると、お見舞い封筒に名前を書くことは必須というマナーが分かり、驚くと同時に自分も知っておかなければならないと思いました。
そんな経験を経た上で、今回は「お見舞い封筒に名前は書かないことは、実はマナー違反になる」ということについて、備忘録を添えて、共有していきたいと思います。
ぜひ最後まで読んでください!
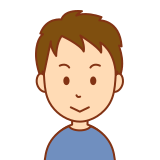
-150x150.jpg)
お見舞い封筒に名前は書かないのはダメ!書くべき理由とは?

冒頭でお伝えした通り、お見舞い金を贈るとき、「封筒に名前を書くかどうか」で迷った経験がある人もいると思います。私も封筒に名前を書くのが一般的なのか疑問に思ったことがありました。
「お返しは不要だから名前は書いてない」と思う人もいますが、実は名前を記載するのがマナーであり、相手への思いやりにもつながります。自分の名前を書かないと、受け取った相手に不便や気遣いをさせてしまうことがあるため注意が必要です。
ここでは、お見舞い封筒に名前を書くべき理由を4つの観点から解説します。
- 相手が誰からのお見舞いか認識できるため
- お返しの際に手続きがスムーズになるため
- 贈り主の誠意や心遣いを伝えるため
- 日本の文化的・社会的背景としての理由
上記の4点について、解説していきますので、名前を書くべき理由を理解していきましょう!
相手が誰からのお見舞いか認識できるため
お見舞い封筒に名前がないと、お見舞いを受け取った相手は誰から届いたのかがわからず、かえって不安や戸惑いを与えてしまうことがあります。
特に入院中や療養中は体調が万全ではなく、贈り主を特定するためのやりとり自体が負担になることもあります。封筒に自分の名前を明記しておけば、受け取った瞬間に相手が安心でき、感謝の気持ちをすぐに持ってもらえます。
お返しの際に手続きがスムーズになるため
入院中にお見舞いを受け取った場合、多くの人は退院や快復後にお礼や「快気祝い」を贈ります。
封筒に名前がないと、お見舞いを受け取ったはいいものの、誰にお返しすれば良いのかがわからず、お返しの手配が遅れてしまったり、誤って贈ってしまう可能性もあります。
お見舞い封筒に自分の名前を記載しておけば、相手はスムーズにリストなどを作成し、漏れなくお礼を贈ることができるため、双方にとって気持ちの良いやり取りが可能になります。
私もこの、「双方にとって気持ちの良いやり取りが可能」ということを重要視しています。せっかくお金や何かものを贈るのですから、お互いに気持ち良くやり取りしたいですよね。
贈り主の誠意や心遣いを伝えるため
お見舞い封筒に名前を記すことは、形式的なマナーであると同時に、相手への誠意を表す行為でもあります。
お見舞い封筒に名前を書かず、匿名だと、「誰がくれたのか分からない・・・」「本当に気持ちがこもっているのかな・・・」という疑問や不安な気持ちを抱かせる場合が出てきてしまいます。
しっかり自分の名前を書くことで、「あなたを思って贈った」という気持ちが伝わり、より温かみのあるお見舞いになります。
お見舞い封筒に名前を書くだけで、相手への誠意を表せるのですから、よくなってもらいたい気持ちを込めて贈るのでしたら、ぜひ名前を書きましょう!
日本の文化的・社会的背景としての理由
日本では昔から、贈答品やお金の入った封筒には贈り主の名前を書くことが礼儀とされています。
これは「贈る行為」と「受け取る行為」を明確にし、感謝やお返しの文化を円滑にするための慣習です。
よって、少なくとも日本では、お返しは返すべきというよりも、返さなければいけないという義務感があるものになります。
■もちろんお見舞いの場合も同じ
冠婚葬祭などのイベントだけでなく、お見舞いでも同様のマナーが重視されます。
なので、お見舞い封筒に自分の名前を記載することは、単なる形式ではなく、日本の文化や人間関係を大切にする心の表れでもあります。また、自分の名前を書くことで気持ちよく自分の気持ちを相手に伝えることができるので、社会的にもマナーのよい人だと思われることでしょう。
お見舞いの封筒に名前を書かないことで起きる心理的影響
お見舞い封筒に名前を書かないことは、悪意を持って行うことではありません。
多くの場合ですが、贈る側は「相手のため」と思ってあえて書かないという選択をしており、善意からくる行動です。
しかし、その善意が必ずしもお見舞いを受け取る側に正しく伝わるとは限らないため、結果的に戸惑いや不安を与えてしまうことがあります。この章では、以下の通り、贈る側と受け取る側のそれぞれの心理的な影響を見ていきましょう。
- 贈る側の心理
- 受け取る側の困惑
こちらの、贈る側と受け取る側のの心理的な影響を考えることで、お互い気持ちよくやり取りできることになります。
贈る側の心理
まず贈る側の心理を理解します。
本章冒頭でお伝えした通り、贈る側は決して悪意があって名前を書かないという選択をしているわけではなく、受け取る側の相手を思って、名前を書かないという選択をしています。
贈る側の名前を書かないという選択の理由は以下のような場合が考えられます。
- お返し不要の意思表示:
名前を書かないことで「お返しはいらないです」という気持ちを示している場合があります。特に、相手側の経済的・精神的負担を減らすために、あえて封筒に名前を書かないで渡すという考え方です。 - 相手への負担軽減のつもり:
病気や怪我で入院している人にとって、お礼の連絡やお返しの準備は体力的にも精神的にも大きな負担です。贈る側は「名前を伏せればお礼の連絡もしなくて済むし、相手も楽になるだろう」と考えるため、名前を書かないケースがあります。 - 純粋な善意を示したい:
相手に見返りを求めず、純粋に相手の回復を願う気持ちから、あえて名乗らないケースもあります。いわば「無償の愛」を示すつもりでの行動ですが、これは日本ではやや珍しい文化であり、誤解を招いてしまう場合があります。
このように、贈る側の名前を書かないという選択の心理としては、受け取る側の相手のことを思った行動です。
私も受け取る側の相手からのお返しが不要と思うこともあるので、名前を書かないという選択をしたいところですが、お返しをすることは当然と思ってる相手側からすると、逆に負担となってしまいますね。
受け取る側の困惑
次に受け取る側の相手の心理を理解します。
名前が書かれていないお見舞い封筒を受け取ると、当然のことながら後々見た時に、誰からのお見舞い封筒か分かりません。
すると、お返しをしたくても誰からいただいたものか分からないので、お返しができなくなってしまうんですね。
- 感謝を伝えられない:
お見舞いが誰から届いたのか分からないため、「ありがとう」とお礼を直接伝えることができません。お礼を伝えられないことは、受け取る側にとっても心残りとなり、モヤモヤした気持ちが残ってしまいます。 - お返しができない:
退院するなどして、快復後に快気祝いを贈ろうとしても、贈り主が分からないためお返しを贈ることができません。日本ではお見舞いへのお返しが慣習として根付いているため、お返しできないことを失礼と感じる人も多くいます。 - 気持ちが宙ぶらりんになる:
名前がない贈り物は、相手に感謝や交流のチャンスを奪ってしまうこともあります。「この贈り物は誰だろう?」という疑問だけが残り、本来の温かい気持ちが十分に届かないまま終わってしまう可能性があります。
上記のように、名前が書かれてないお見舞い封筒を受け取ると、お返しをすることが当然と思ってる人は、お返しができず、心残りがでてきてしまいます。
お返しすることが当然と思ってる人が多いので、失礼に感じてしまう人も出てきてしまいます。私もお返しすることが普通と考えているので、失礼に思ったり、モヤモヤとした気持ちが残ってしまいます。
また、私も「これは重要なこと」だと思っていることがあります。贈ってくれた相手との交流のチャンスがなくなってしまうということです。せっかくお金を贈ってくれたのですから、しっかりお返しをしたいと思うのは、日本にいる人にとっては、マナーになるのです。
どうしても名前を書きたくない場合の代替案

お見舞い封筒に名前を書くのが望ましいことはわかっていても、個人的な事情や立場上、どうしても名前を伏せたいケースもあります。
例えば、相手との関係性が微妙な場合や、職場全体のいちメンバーとして匿名で贈りたい場合などです。そんなときでも、受け取る側に戸惑いや不安を与えないためには、「名前を完全に伏せる」のではなく、別の形で贈り主が分かる工夫を取り入れることが大切です。
ここでは、お見舞い封筒に名前を書かない場合の、現実的な代替案を4つ紹介します。
- 家族や共通の知人を通じて伝えてもらう:
お見舞い封筒に直接名前を記載せず、相手のご家族や共通の友人・知人を通じて「〇〇さんからのお見舞いです」と口頭やメモで伝えてもらう方法です。この方法であれば、相手に感謝の気持ちを届けられ、封筒は匿名のままにできます。 - メッセージカードに名前のみ記載し封筒とは別に渡す:
封筒自体には名前を書かず、小さなメッセージカード等にだけ名前を書き、別添で渡す方法です。受け取った相手は贈り主が分かるので安心し、封筒の見た目や体裁は保てます。 - 代表者名+「有志一同」などで記載する:
職場や団体でのお見舞いの場合は、代表者名と「有志一同」や「〇〇課一同」といった記載方法が使えます。個人名をすべて書かなくても、誰からの贈り物かが明確になり、お返しも代表者を通してスムーズにできます。 - 贈答品や花など現物で贈る際に名前を添える:
お見舞いを現金ではなく、果物やお花などの贈答品でお見舞いを贈る場合は、品物に小さな札やカードを付けて名前を記載する方法もあります。封筒を使わないため名前を書かずに済みますが、受け取る側には贈り主がしっかり伝わります。
上記の通り、少ないケースではありますが、お見舞い封筒に名前を書かない場合もあります。私自身も、会社の同僚が病気で入院された時、上司がまとめてお見舞いを渡してくれたことがありました。
仕事関係の人に渡してもらう方法だと、儀式的な感じにとらえられるかもしれません。ですが、このような場合は、お見舞い封筒に名前を書かなくてもいいので、状況に応じて使い分けましょう!
お返しが不要となるケースは存在する
お見舞いを受け取ったら、基本的には退院後や快復後に「快気祝い」などのお返しをするのがマナーです。
しかし、中にはお返しが不要とされるケースもあります。これはまれなケースで、例外を除けばお返しは受け取る前提で準備しておくべきです。ここでは以下の代表的なお返し不要のケースを紹介します。
- 会社や労働組合から福利厚生としてお見舞金を贈る場合
- お見舞い相手の家族・親族で「お返しは不要」と明言している場合
上記の通り、お返しが不要なケースを理解して、お返しが必要な場合と不要な場合を覚えておきましょう!
会社や労働組合から福利厚生としてお見舞金を贈る場合
企業や労働組合から支給されるお見舞金は、福利厚生制度の一環として渡されることが多く、規定に「お返し不要」と明記されている場合があります。これは個人からの贈り物ではなく、組織的なところからの支給であるため、快気祝いを返す必要はありません。
ただし、感謝の気持ちは忘れず、復職後に口頭やメールなどでお礼を伝えるのが望ましいでしょう。
いくらお返しが不要といっても、回復した後に、口頭などで伝えられるだけで、相手も渡してよかったと思ってくれます。
お見舞い相手の家族・親族で「お返しは不要」と明言している場合
家族や近い親族からのお見舞いで、「お返しはしないで」とはっきり言われることがあります。特に、家族間では経済的なやりとりよりも回復を願う気持ちが優先されるため、このようなケースではお返しは不要とされます。
ただし、本当にお返しが不要かを事前に確認し、後日感謝の言葉や食事に誘うなど、形を変えてお礼を伝えるのが良いでしょう。
上記のような例外は確かにありますが、それ以外のケースではお返しは必要になると考えて行動するのが安心です。お返し不要のつもりで受け取ってしまい、後になって慌てることのないよう、事前の確認と心の準備をしておきましょう。
お見舞いの際に使う封筒に関して知っておきたいポイント
病気やケガで入院している人に「お見舞い金」を包む際には、適切な封筒の選び方やマナーなどをしっかり理解しておくことが大切です。
間違った封筒を選んでしまうと、相手やそのご家族に不快な思いをさせてしまう場合があります。この章では、以下の通り、お見舞いの封筒に関する基本的な知識とマナーを分かりやすく解説します。
- お見舞い用封筒の選び方
- お見舞いとして包む金額の相場
- お見舞い用封筒の書き方
- お金の包み方
- お見舞い金の渡し方
この章を理解すれば、お見舞い封筒に関する、最低限の知識は得られますので、ぜひご覧ください!
お見舞い用封筒の選び方
お見舞い金を包む際には、「のし袋」を使います。ただし、慶事(お祝い事)で使用する紅白の水引がついたものや、不祝儀で使う黒白や黄白の水引は適していません。お見舞いにふさわしい封筒は以下の通りです。
- 赤や紅白の「結び切り」または「結びきりに近い花結び」の水引が描かれたもの
- 「御見舞」「お見舞」「御伺」と表書きが印字されているもの
- シンプルな無地の封筒でも可(小額の場合)

特に病気やケガが「繰り返さない」ことを願って、必ず「結び切り」の水引を選びましょう。
お見舞いとして包む金額の相場
お見舞い金の金額は、贈る相手との関係性やお互いの立場によって異なります。一般的な相場は次の通りです。
| 贈る相手 | 金額の目安 |
| 友人・知人 | 3,000〜5,000円 |
| 職場の同僚・上司 | 5,000〜10,000円 |
| 親戚 | 5,000〜20,000円 |
| 特に親しい関係 | 10,000円以上 |
注意点として「4」や「9」がつく金額は縁起が悪いとされるため避けるのがマナーです。たとえば、4,000円ではなく5,000円、9,000円ではなく1万円としましょう。
お見舞い用封筒の書き方
封筒の表書きは、毛筆や筆ペンを使って書くのが正式です。ボールペンは避け、黒インクを選びましょう。ポイントとしては以下の通りです。
- 表書き:中央上部に「御見舞」または「お見舞」と書く
- 名前:中央下部にフルネームを書く(個人の場合)
- 複数人で包む場合:「〇〇一同」とまとめる
また、裏面には金額を書く欄がある場合は記入しておきましょう。中袋があるタイプの封筒では、中袋の表に金額、裏に自分の住所と名前を書くのが一般的です。
お金の包み方
お札は必ず新札を避け、折り目が少ないきれいなお札を用意します。新札は「準備していた」という印象を与えるため、お見舞いには不向きとされています。
- お札の向きは、人物の肖像が封筒の表側・上向きになるように入れる
- 複数枚ある場合は揃えて同じ向きにする
- 旧札や折り目の少ないものを用意する
心を込めて丁寧に包むことが大切です。
お見舞い金の渡し方
お見舞い金を渡す際には、病室や病院内の雰囲気に配慮しましょう。基本的に病院内は静かなことが前提ですので、大声で話すことはマナー的によくありませんので、注意しましょう。渡し方のポイントとしては以下の通りです。
- 封筒からお金を出さず、そのまま渡す
- 手渡すときは両手で持ち「どうぞお大事になさってください」と言葉を添える
- 病状や状況によってはご家族に渡すこともある
また、次の章でもご説明しますが、相手の体調によっては長居せず、短時間で失礼するのがマナーです。
お見舞いの際にマナー違反となる要注意行動
お見舞いは相手を励ましたり応援するためのものですが、無意識の行動がマナー違反になり、かえって迷惑をかけてしまう場合があります。ここでは、お見舞いで特に注意すべき代表的なNG行動を5つ取り上げ、具体的に解説します。
- 面会時間や渡すタイミングを守らない
- 長時間の滞在や騒がしい言動をする
- 派手な服装や喪服で訪問する
- 鉢植えや縁起の悪い花や、香りの強い花を贈る
- 現金をそのまま渡す
このようなNG行動は、入院している人に失礼にあたりますので、しっかり理解して、気持ちの良いお見舞いの場面にしましょう!
面会時間や渡すタイミングを守らない
病院には面会時間が定められており、それを守らないと治療や休養の妨げになります。
また、手術直後や検査の直前などは避けるのがマナーです。これは病院だけでなく、入院してる相手本人にも迷惑がかかりますので、訪問前に必ず病院や家族へ確認しましょう。
時間を守ることは社会人としてのマナーですが、渡すタイミングは病院や本人の状況によって、変わってくるので、事前連絡が大切です。
長時間の滞在や騒がしい言動をする
お見舞いは相手の体調を第一に考えるものです。長居したり、大人数で押しかけたり、大きな声で話すなどの行為は相手の休養を妨げてしまいます。目安は10〜15分迄の短い滞在が理想です。
以下の表を参考に、短い時間の滞在を心がけましょう。
| 滞在の仕方 | 印象・影響 |
| 10〜15分迄 | 相手に負担がなく理想的 |
| 30分以上 | 相手の体調によっては負担 |
| 1時間以上 | 相手の休養を妨げるNG行動 |
入院してる相手とゆっくりお話ししたい場合もありますが、ゆっくり話す場合は、退院してからにしましょう!
派手な服装や喪服で訪問する
派手すぎる服装は病室の雰囲気にそぐわず、喪服は不吉な印象を与えます。お見舞いには、落ち着いた色合いの普段着が適切です。
男性の場合は、スーツでも問題ありませんが、派手なネクタイなどは避けましょう。私服の場合でも明るい色の服装や清潔感のある落ち着いた服装にするよう心がけましょう。
女性の場合も同様に、派手な色合いの服装は避けましょう。明るい色合いで落ち着いた服装が理想的です。
鉢植えや縁起の悪い花や、香りの強い花を贈る
鉢植えは「根付く=寝付く」と連想され、病気が長引くイメージがあるため避けるのがマナーです。
また、菊や椿など葬儀を連想させる花、香りの強い花も病室には適切ではありません。代わりに、明るい色合いの切り花やアレンジメントがおすすめです。
花を贈る場合は、その花の種類も大切ですね!
現金をそのまま渡す
お見舞い金は必ず封筒に包んで渡すのがマナーです。
これは、お見舞いに限った話ではありませんが、現金を裸のまま手渡すのは、相手に対して失礼にあたります。お祝い事や周りで不幸があった場合も、現金をそのまま渡すのではなく、封筒に包んで渡すことようにしましょう。
受け取る側を考えると、現金をそのまま渡されると良い気持ちにならないと思うので、相手のことを思いやり、しっかりマナーを守りましょう!
まとめ
この記事では、お見舞い封筒に名前は書かないことはマナー違反ということの理由や、贈る側/受け取る側の心理的な面、お見舞い封筒に関わるマナーのポイントや要注意行動などについて、解説してきました。
本記事で解説してきた通り、一部の例外を除いて、お見舞い封筒には自分の名前を書くことがマナーです。
お見舞いの場面など、相手にお金や物を贈る場合は、相手の気持ちを大事にしてマナーを守ることがお互いに気持ち良い受け渡しとなります。
お見舞いに限らず、こういった社会人としてのマナーを学び、理解しておくことは一過性のものではなく、今後ずっと使える知識です。
こういったことを理解しておき、いざ使う場面が発生したら、慌てず、マナー通りにやり取りすることで、「この人は分かってる」と社会人として認められる存在になれますので、日頃からアンテナを張っておきましょう!



コメント